「説明しても相手が理解してくれない…」
「言葉が足りなかったのかな?」

そんなモヤモヤ、感じたことはありませんか?
実は、それはあなたの説明が下手だからではありません。
人は、知らない話や難しい話に出会うと、無意識に“拒否反応”を示す心理的な傾向があるのです。
でも、ここで“あるスキル”を使うだけで、相手の頭にスッと届く説明ができるようになります。
それが「例え話」です。
たとえば「コンピュータのメモリ」と言われても、ピンとこない人は多いでしょう。
でも「作業机の広さ」と置き換えれば、すぐにイメージできるはずです。
この記事では、“例え話”を使って難しい概念を分かりやすく伝える4ステップを紹介します。
マーケティング、教育、ライティング…どんな場面でも使える実践的なスキルなので、説明が苦手な方はぜひ活用してみてください。
「難しい話は聞きたくない」が脳の本音
「難しい話は聞きたくなーい」

あなたも、少し難しい話が出た瞬間に、相手が露骨に表情を曇らせたり、聞き流しモードに入るのを見たことはありませんか?
これは単なる興味の問題ではなく、脳の防衛反応が原因です。
心理学や脳科学でも、理解が難しい情報は脳にストレスを与えるため、無意識に避けようとすることが分かっています。
たとえば、会議で専門用語ばかりの説明を受けると、理解できずに聞き逃したり、つい別のことを考えてしまう。
多くの人が経験するこれが、まさに“脳のイヤイヤ反応”です。
では、このイヤイヤ反応をどうやって解消するのか?
答えはシンプルです。
相手が「知っている何か」と結びつけること。
人は、自分の関心や生活に関係する話であれば、自然と理解しやすく、受け入れやすくなります。
つまり、難しい話を“身近な例”に置き換えることで、脳のイヤイヤを解除できるのです。
例え変換の4ステップ
「なるほど、身近な例に置き換えればいいんだな!」
「よしやってみよう!」
……でも、いざやろうとすると手が止まる。
心配いりません。
分かりやすい説明はセンスではなく、手順で身につけられる技術です。
ここでは、難しい話を身近な例に変換するための「4ステップ」を紹介します。
ステップ1:概念を一文で要約する
「クラウド」という用語を例に考えてみましょう。
一般的な定義はこうです。
クラウドとは、インターネット経由でサーバーやストレージ、ソフトウェアなどを利用する形態のこと。
正直、初心者にはイメージしづらいですよね。
ここでやるべきはシンプルに一文で要約すること。
「クラウド」 → 「ネット上でデータを預ける仕組み」
これでぐっと分かりやすくなりました。
ステップ2:本質を抽出する
次に「この概念の本質は何か?」を考えます。
クラウドの本質はこう整理できます。
「どこからでもアクセスできる」
「自分で管理しなくていい」
この“本質”を抜き出すことで、日常にある似たものを探しやすくなります。
ステップ3:日常にある類似モデルを探す
では、この本質と同じ性質を持つものは何でしょう?
「どこからでもアクセスできる」 → インターネット、スマホ
「自分で管理しなくていい」 → 貸し倉庫、図書館、レンタカー

身近なモデルが見えてきましたね。
ステップ4:ストーリー化する
最後に、これらをつなげて説明をストーリーにします。
「クラウドは、インターネット上にある貸し倉庫みたいなもの。自分のスマホに保存しなくても、どこからでも写真や文書を見られる仕組みです。」
最初の専門的な定義より、ぐっとイメージが湧きやすくなったはずです。
この「要約 → 本質 → 類似モデル → ストーリー化」の4ステップを使えば、どんな難しい話も相手がスッと理解できる説明に変えられます。
シンプルな説明が大事
「あれ?この説明って、クラウドのファイル保存の話しかしてないけど…?」
はい、その通りです。
クラウドには他にも機能がありますが、ここではあえて「ファイル保存」だけに絞りました。
なぜなら、人は一度に複数の新しい情報を処理すると、注意が分散して理解が浅くなりやすいからです。
だからこそ、まずは一番イメージしやすい側面に絞って説明するのが効果的。
例え話は「全部を説明する道具」ではなく、「入り口を作る道具」なんです。
ゴテゴテした説明より、シンプル・イズ・ベスト。
だからこそ、例えの力が活きるんです。
他の例で見る「日常翻訳」
なんとなくイメージを掴んでいただいたところで、もう少し例を見てみましょう。
先に紹介した4ステップを使うと、ちょっと難しそうな用語でも簡単に説明することができます。
実際に少し難しい概念を身近な例でたとえてみます。
✅プロンプト
【定義】
プロンプトとは、AI(生成系AI)に対するユーザーからの指示・入力文であり、AIがどのような出力を生成するかを具体的に規定・誘導する役割を持つもの。
【言い換え例】
AIという料理人にどのような料理を作ってほしいかを伝える注文票のようなもの。
ステーキを作ってほしいなら、どのような肉を使うか、焼き方はどうするか、ソースの味付け、添え物をどうするかを詳細に伝えないとAIが勝手にすき焼きを作ってしまう。

→ このように言い換えることで、「指示の精度が結果を左右する」というプロンプトの本質が一瞬で理解できます。
✅クッキー
【定義】
クッキーとは、ウェブサイトがユーザーのブラウザに送信・保存するデータファイルであり、ユーザーの再訪問を識別したり、セッション情報、サイト上の設定や状態を保持・管理するために利用される技術である。
【言い換え例】
美容室のスタンプカードのようなもの。
美容室(サイト)に再訪すると「前回来たお客さんですね」と分かり、前回来た時のカット内容や好み(サイト上の設定等)も覚えていてくれる。
→ 難解なウェブ用語も、日常の体験に置き換えると直感的に理解できるようになります。
✅ビットコイン
【定義】
ビットコインとは、分散型台帳技術であるブロックチェーン上に記録・管理される暗号資産の一種であり、インターネット上で価値の交換手段として機能するデジタル通貨である。
【言い換え例】
インターネット上にあるデジタルのお金のこと。
誰も勝手に増やせないから価値が保たれ、一部のお店では実際に物を買うこともできる。
→ 「投機的なイメージ」が先行しがちなビットコインも、日常の例に置き換えると“デジタル資産”としての本質がスッと腑に落ちます。
このように難しそうに見える言葉ほど、日常のイメージに変換した瞬間に「そういうことか!」と理解が加速します。
これは単なる比喩ではなく、専門知識を“脳が処理できる言葉”に翻訳する技術です。
つまり、あなたもこの4ステップを使えば、どんなに難しい話や複雑な概念でも「誰にでも伝わる言葉」に変換できるようになるのです。
マーケティング・教育・ライティング等への応用
言い換えができるようになると説明がうまくなる!
実は、この技術って単に「説明がうまくなってよかった!」で終わるものではないんです。
この「日常翻訳」のスキルは、あらゆる分野で即戦力になります。
単に「分かりやすい説明ができる」だけでなく、相手の理解スピードを上げ、行動を引き出す力に直結するのです。

たとえば、以下のような場面でも応用することができます。
マーケティング
商品やサービスを「日常の体験」に置き換えるだけで、伝わり方が劇的に変わります。
例:「最新型CPU搭載スマートフォン」=「脳が通常の3個分あるスマホ」
→ スペックの数字ではなく「体感できるイメージ」に変換することで、購買意欲が湧きやすくなります。
ポイント:数字や専門用語は“比較”より“感覚”に翻訳する。
教育
抽象的な理論も、身近な現象に例えることで記憶に定着します。
例:「重力」=「ボールを落とせば必ず下に落ちる“世界のルール”」
→ 難しい公式よりも、まずは目に見えるイメージで説明した方が理解が早くなります。
ポイント:「まずイメージ、その後に理屈」の順で説明する。
ライティング
専門知識を「友達に話す感覚」で噛み砕けば、読みやすさが一気に上がります。
例:「AIの学習」=「クイズ番組で何度も問題を解いて答え方を覚えるみたいなもの」
→ 専門的な説明を減らし、身近なストーリーで語ると、最後まで読んでもらいやすくなります。
ポイント:専門用語を先に説明せず、例え話で“入口”を作る。
このように、日常翻訳はただ分かりやすくするためのスキルではありません。
「分かりやすさ」を武器に、理解・記憶・行動を加速させる技術なのです。
まとめ
・例えは「難しい」を「分かる」に変える翻訳機
・「一文要約 → 本質抽出 → 日常モデル → ストーリー化」の4ステップで誰でもできる
・マーケティング・教育・コンテンツ…どの分野でも強力な武器になる
難しい話を日常で語れる人は、それだけで「分かりやすい人」になり、結果的に影響力も上がります。
💡 次の一歩
「AI」「ブロックチェーン」「インフレ」など、よく聞くけど説明しづらい用語をひとつ選んでみてください。
そしてこの4ステップで、日常の例に置き換えてみましょう。
それができれば、あなたも“伝わる人”の仲間入りです。
まずは1つ、あなたも試してみてください。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
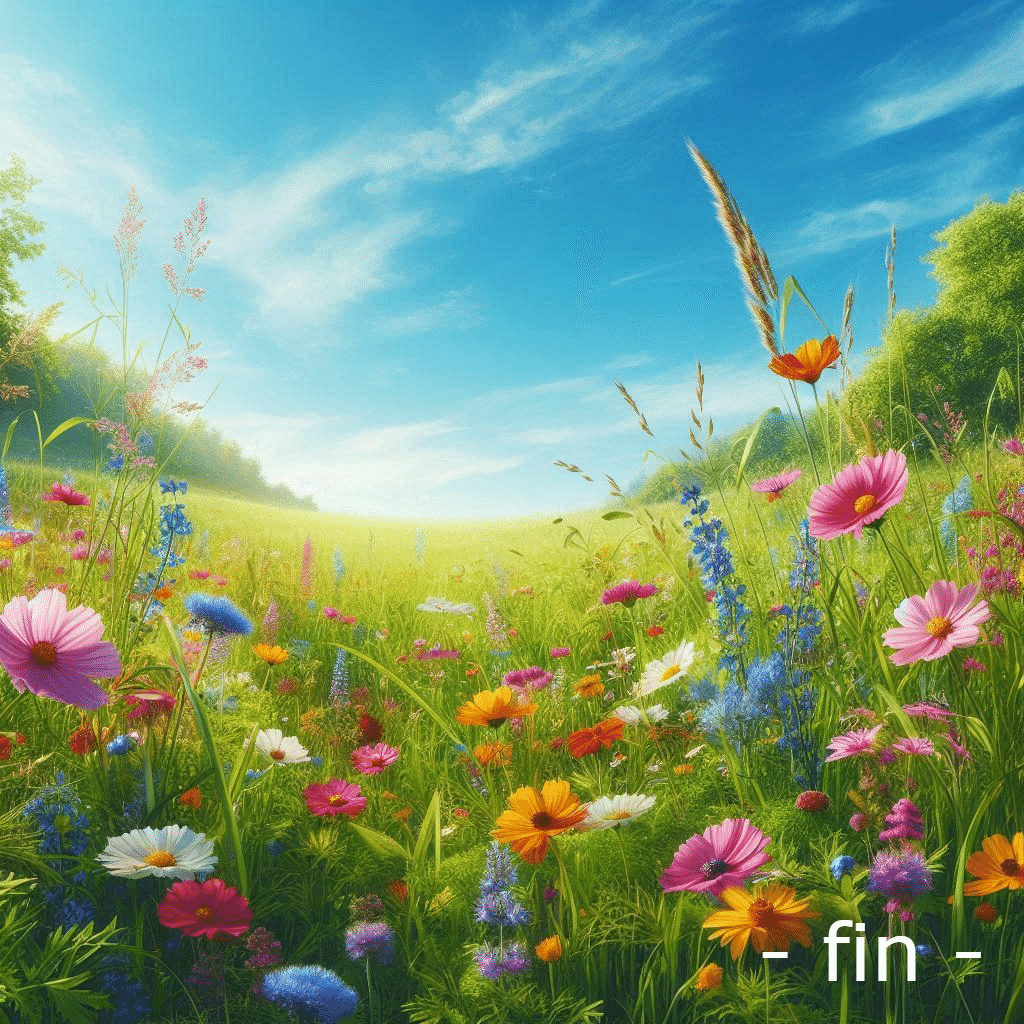

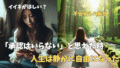

コメント